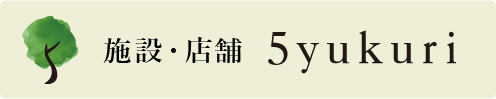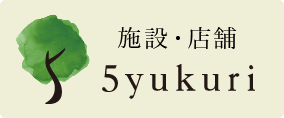スタッフの丸山です。 幾分か朝晩も涼しくなり秋の気配を感じるようになってきましたね♪
ちょうど会社の周りの田んぼも稲刈りシーズン!
ついこの間まで青々と風になびいていた稲穂も今では黄金色に。
早く新米が食べたいですね♪
先日、弊社が所属するガーデンサービス研究会主催の自然の植生観察研修会へ参加するため
長野県は菅平へ行ってきました!
そもそも植生(しょくせい)とは。。。
ある地域に自生している植物全体のまとまりのことです。
森林、草原、畑など特定の場所を覆っている植物全体を指します。
気候や土壌などの条件により植生は異なり、見た目の特徴で森林、草原、荒原などに大別されます。
そしてその植生が時間とともに変化する植生遷移(しょくせいせんい)段階を学べる場所と機会がたくさんあるということでここ菅平へ。 今回、ガイドを務めるのは「やまぼうし自然学校」代表の加賀美さん。
今回、ガイドを務めるのは「やまぼうし自然学校」代表の加賀美さん。
信州の森で一年を通し子供から大人まで楽しめる体験活動を主催されております。
ちょっとした座学の後に実際にトレイルコースに入り植生遷移を学びました!  牛がお出迎え! この辺りは標高1500m、夏だけこちらの頂上付近で放牧され草を食べ草原を維持しています。 縄文土器が発掘されるくらい古くから利用されてきた土地だそうです。
牛がお出迎え! この辺りは標高1500m、夏だけこちらの頂上付近で放牧され草を食べ草原を維持しています。 縄文土器が発掘されるくらい古くから利用されてきた土地だそうです。  ここに生えているシダ類はゼンマイ。
ここに生えているシダ類はゼンマイ。
アク抜きしないと食べられないのは牛も同じ。
レンゲツツジにも毒があるので低木類で多く見られます。
大群生地もあり、このあたりの春を彩ります。 
なんと言っても白樺。
これでもか!てくらい白樺です。
先駆樹種と言って草原に最初に生えるのがこの辺りでは白樺。
60年前はこの辺も草原だったそうです。
 笹の花を見ることが出来ました。数十年に一度開花し地下茎で繋がったササ全体が一斉に枯れ、世代交代をします。 日当たりや条件によって、また別の植物が生えたりと森の形も変化していくのだそうです。
笹の花を見ることが出来ました。数十年に一度開花し地下茎で繋がったササ全体が一斉に枯れ、世代交代をします。 日当たりや条件によって、また別の植物が生えたりと森の形も変化していくのだそうです。 
 個人的にはこういった景色がたまらなく好きです。キュンです(笑)
個人的にはこういった景色がたまらなく好きです。キュンです(笑) 
 特別な許可を頂いての土壌観察。 知っていましたか?土が出来るまでとんでもない時間が掛かることを。
特別な許可を頂いての土壌観察。 知っていましたか?土が出来るまでとんでもない時間が掛かることを。
気になる方は「土が出来るまで」で検索お願いします!
気温や場所の条件にもよりますが1cm出来るのに約100年掛かると言われています。
それにしても森の土はふっかふか♪
握り固めてもほろほろとすぐにほどける団粒構造
お庭造りにもぜひ再現し取り入れたいです。 何年かかるのかなぁ
 石の上の小宇宙。
石の上の小宇宙。
何かの原因で転げ落ちた岩に、それこそとんでもなく長い年月を掛け降り積もった土に根を下ろした植物たち。
とんでもないロマンがありますよね! わかってくれる方いらっしゃいますか?  トリカブト。実際に見たのは初めてでした。
トリカブト。実際に見たのは初めてでした。
ただただ美しい。
猛毒につき触るな危険ですよ!  雲が掛かり山並みは見えませんでしたが心の眼で見てきました!
雲が掛かり山並みは見えませんでしたが心の眼で見てきました!
美しい山並みでした(笑)  二日目は数百メートル下り、ダボスの丘の探索。
二日目は数百メートル下り、ダボスの丘の探索。
冬場はスキー場のこのエリア、夏場は色とりどりの植物が咲き、植物が種を落とした秋に刈り取るのだそうです。
ワレモコウの群生や、普段お庭で良く植えるマツムシソウやアザミ。
湿った場所に生えているイメージのアヤメも実はこういった明るく乾燥した斜面に群生していたりと、沢山の学びがありました!

そして研修の最後は唐沢の滝へ。
岩肌の感じ好きだわ~、木々、水量。。。
滝ランキング暫定一位に躍り出ました!
ちょうど秋に滝組みの現場があるので、近づけたいですね!
 森の中を歩きわかったことは、まさに植生の変化。
森の中を歩きわかったことは、まさに植生の変化。
いままで何気なく見てきた景色も、プロセスを知ることで全然見え方が変わりました!
植物たちが共存し自分の心地のいい場所に根を下ろす。
石や樹木に草花たち、今まで以上に特性を理解し植え込んでいく。
人も植物にとっても心地の良いお庭造りをしていかなければと強く思った今回の研修になりました。


そして念願叶ってようやく長野市の北野美術館にも伺えました。
世界的にも著名な作庭家、重森三玲氏の枯山水庭園。
作庭から60年。
当然ですが本で見るのと実際に見るのとではまるで違いますね!
凄まじいエネルギーをもらいパワーアップした丸山にこうご期待!それではまた!